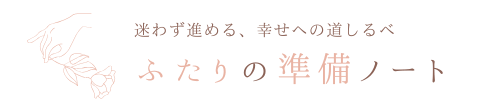結婚の準備が進む中で、多くの人が迷うのが結納返しです。結納を行うことになった場合、相手方のご厚意に対してどのようにお返しをすればよいのか、またそもそも返礼が必要なのかと悩む方は少なくありません。
地域や家庭の慣習によっても考え方が異なり、両家の出身地や家族の価値観が重なると、より複雑に感じられることもあるでしょう。結納返しには金額の相場や選ばれる品物、渡すタイミングなど、知っておきたいポイントが多くあります。
本記事では、結納返しの基本から地域差、相場、品物選び、マナーまでをわかりやすく整理し、自分たちに合った方法を判断できるように解説します。
結納返しとは?基本の意味と役割

結納返しとは、結納の場で新郎側から贈られる結納金や結納品に対して、新婦側から感謝の気持ちを込めて行うお返しのことを指します。
結納そのものは、両家が婚約を正式に確認し合う伝統的な儀式であり、結納返しはそのやり取りをより円満に整える役割を果たしてきました。かつては「結納金の半額を返す」といった明確な形式が存在し、贈答品として高級時計やスーツ、学業や仕事に役立つ品物などが選ばれることが一般的でした。
返礼は、単に金銭的なやり取りではなく、「娘を大切に育てていただいたことへの感謝」「これからよろしくお願いします」という新婦側の誠意を表す意味合いも含まれています。また、結納返しは両家の関係を円滑に保つための象徴的な行為でもあり、婚約という大切な節目をより確かなものにする役割を持ちます。
近年では形式を簡略化したり、記念品だけにとどめたりと多様化が進んでいますが、本来の意義は「両家の絆を深めるための大切な心配り」にあるといえます。
結納返しの必要性はある?最近の傾向と割合
現代において、結納返しを必ず行わなければならないという決まりはありません。実際に、結納そのものを省略して顔合わせ食事会で済ませるカップルも増えており、結納返しも同様に簡略化や省略の傾向が見られます。
近年の調査では、結納を行ったカップルの中でも「きちんと結納返しを用意した」という割合は過半数を下回り、代わりに「記念品として贈った」「親からお返しは不要と言われた」などのケースも多くなっています。この背景には、地域慣習の変化に加え、共働き世帯の増加や式準備にかかる費用負担の見直しがあります。特に都市部では「返礼はしなくてもよい」という考え方が広がりつつあります。
一方で、地方では「最低限の形は整えるべき」という意識が根強く残っています。そのため、必要性の有無は両家の意向によって大きく異なります。重要なのは、一方的に判断するのではなく、両家で十分に話し合いを行い、互いに納得できる形を見つけることです。
返すかどうかに明確な正解はなく、二人の新しい生活に支障をきたさない範囲で、感謝の気持ちを形にすることが求められています。
結納返しの形式と地域差
結納返しの方法は全国一律ではなく、地域や形式によって大きな違いがあります。特に関東と関西では返礼の割合や品物の選び方に特徴があり、両家の出身地が異なる場合には判断に迷うことも少なくありません。ここでは代表的な形式を整理し、地域ごとの特徴を解説します。
関東式の特徴と返礼方法
関東地方では、結納返しは「結納金の半額を返す」という考え方が一般的です。これを「半返し」と呼び、現金で返す場合もあれば、記念品を添えて渡す場合もあります。
代表的な記念品としては、高級腕時計やスーツ、万年筆など長く使える品物が選ばれることが多く、新郎が社会人として活躍する場面を意識した実用的なアイテムが好まれます。また、返礼にあたっては金額のバランスを重視しすぎず、「感謝の気持ちを示す」という本来の意義を意識することが大切です。
関東式では儀式全体も比較的簡略化される傾向にあり、顔合わせと同時に行うケースも増えています。そのため、返礼の内容も柔軟で、両家が納得できる範囲で調整することが推奨されます。
形式にとらわれすぎず、両親の意向を確認しながら準備を進めることで、無理のない形で結納返しを整えることが可能です。
関西式の特徴と返礼方法
関西地方では、結納返しの考え方が関東とは大きく異なり、一般的に「結納金と同額を返す」とされています。つまり、結納金が100万円なら、その全額に相当する品物や金銭を返礼するのが慣例です。このため、関西式では結納返しの負担が比較的重く感じられることもあります。
返礼の方法としては、現金だけでなく「記念品+現金」といった組み合わせがよく選ばれます。例えば高級腕時計やブランドバッグ、さらには新居の家電や家具など、結婚後の生活に役立つ実用性の高いアイテムが選ばれる傾向があります。また、関西は格式を重んじる地域性もあり、熨斗や水引の細部にまで気を配ることが求められる場面もあります。
ただし最近では、経済的な負担やライフスタイルの変化から、関東式にならって「半返し」にする家庭も増えてきています。大切なのは伝統を尊重しつつも、両家の意向や現実的な事情に合わせた返礼を選ぶことです。
略式結納や地域ごとの違い
近年では、結納を正式な儀式として行わず、簡略化した「略式結納」を選ぶカップルも増えています。略式結納では、結納金や結納品の数を減らし、進行もシンプルにまとめるのが特徴です。例えば、料亭やレストランでの食事会に合わせて結納金の受け渡しだけを行うスタイルや、結納金に代えて記念品を交換するスタイルなどがあります。
地域によっても簡略化の度合いは異なり、都市部では「顔合わせ食事会+簡単な返礼」のみで済ませるケースが多く見られます。一方、地方では伝統を重視する家庭が多く、結納返しも略式ながら「最低限の形は整える」ことが求められることがあります。また、親世代の意向や親戚からの目も影響するため、同じ地域内でも家庭ごとに差が出やすいのが実情です。
重要なのは、形式の厳格さにとらわれるのではなく、両家の価値観を尊重し合い、納得できる方法を選ぶことです。略式結納は経済的・時間的な負担を抑えながらも、両家のつながりを確認する大切な機会であり、柔軟に活用できる選択肢といえるでしょう。
両家の出身地が異なる場合の対応
結納返しで特に悩ましいのが、両家の出身地が異なる場合です。関東と関西のように慣習が大きく異なる地域同士では、「半返しが基本」と「同額を返すのが一般的」という考え方が衝突することもあります。
こうした場合、どちらか一方のやり方に完全に合わせると、もう一方の家族に不満が残る可能性があります。そのため、両家の間で事前にしっかり話し合い、双方が納得できる折衷案を見つけることが大切です。
例えば「結納金の3分の1を返し、記念品を添える」といった中間的な方法や、現金ではなく双方に意味のある品物で返すといった工夫も可能です。また、ホテルや結婚式場が提供する結納プランを活用すると、専門スタッフのアドバイスを受けながら地域の慣習を調整できるため安心です。
最終的に重視すべきは、形式の正しさよりも両家が気持ちよく結婚を迎えられることです。両親や親族に相談しつつ、無理のない方法を選択することで、異なる慣習がある場合でも円満に結納返しを整えることができます。
結納返しの金額・相場

結納返しを検討するうえで、多くの人が最も気になるのが金額の相場です。返すべき金額は全国で一律ではなく、地域や家庭の考え方によっても異なります。ここでは全国的な平均や、関東・関西それぞれの目安を確認しながら、無理のない返礼の仕方を考えていきましょう。
全国的な相場と平均額
全国的に見た結納返しの目安は、結納金の「半額程度」とされています。たとえば結納金が100万円なら50万円前後が一般的な基準となります。ただし、返す方法は現金だけではなく、記念品の購入や一部を贈答品に充てる場合も多く、家庭によって工夫が見られます。
近年は結納そのものを省略するカップルが増えた影響で、返礼金額も縮小傾向にあり、全国的な平均では20万~50万円程度に収まるケースが目立ちます。都市部では「顔合わせ食事会のみ」で済ませる家庭も多く、その場合は形式的な返礼が行われないことも珍しくありません。
一方、地方や伝統を重んじる家庭では、従来通りの金額を準備してきちんと返すことが尊重されます。つまり、全国的な相場はあくまで参考値であり、最終的には両家の価値観や経済状況に合わせて調整することが大切です。金額よりも相手のご厚意にどう応えるかという姿勢が、結納返しの本質だといえるでしょう。
関東・関西での金額目安
地域ごとに見ると、関東と関西では返礼金額に大きな違いが表れます。関東では「半返し」が一般的で、結納金の半額を返すことが目安とされています。例えば結納金が100万円なら、50万円程度を現金または記念品で返すケースが多いです。
これに対し、関西では「同額返し」が伝統的な考え方で、100万円の結納金に対して100万円相当を返すのが慣習とされてきました。そのため関東と比べて負担が大きく、金額の違いが両家間の調整課題になることもあります。
ただし現代では、関西でも半返しを取り入れる家庭が増え、形式にとらわれすぎず柔軟に判断する流れが見られます。地域ごとの金額目安は参考になりますが、必ずしもその通りに従う必要はなく、両家の意向を尊重しつつ現実的な範囲で決めることが重要です。
現金で返す場合の注意点
結納返しを現金で行う場合は、金額の目安だけでなく、渡し方やマナーにも気を配る必要があります。まず、金額は地域の慣習を踏まえつつ、両家の負担感が偏らない範囲で設定することが重要です。包む際には新札を用意し、折り目のないきれいなお札を使うのが基本的なマナーとされています。
封筒は紅白の水引が印刷された「のし袋」を選び、表書きには「御礼」や「結納返し」と記すのが一般的です。また、金額が大きい場合は銀行で両替を済ませ、枚数や扱いに注意して準備しましょう。
渡すタイミングは結納当日が多いですが、略式の場合や日程の都合により後日手渡すこともあります。その際には挨拶状を添えると丁寧な印象を与えられます。現金だけではそっけない印象を与える場合があるため、時計やスーツなど実用品を添えると心遣いが伝わりやすくなります。大切なのは、形式だけでなく「感謝の気持ちが伝わる渡し方」を意識することです。
結納返しをしないケースと理由
現代では、結納返しを行わないケースも珍しくありません。その理由のひとつは、結納自体を省略するカップルが増えている点です。顔合わせ食事会のみで済ませる場合、結納金の受け渡しがないため返礼の必要もなくなります。
また、両家の話し合いで「結納返しは不要」と合意するケースもあります。特に新郎側から「これからの生活資金に充ててほしい」との意向がある場合は、返礼をしないことがむしろ歓迎されることもあります。
とはいえ、結納返しをしない場合でも、記念品や感謝の言葉を添えるなど、気持ちを表す工夫を取り入れると、相手に誠意を伝えることができます。重要なのは、返すかどうかではなく、両家が納得できる形を選び、円満な婚約のステップとすることです。
結納返しの品物は何を選ぶ?おすすめ3選
結納返しは現金だけでなく、品物として贈ることも一般的です。伝統的に選ばれる縁起物から、現代的な実用品まで幅広い選択肢があります。ただし、何を贈るかは両家の考え方や地域の慣習に左右されるため、意味や用途を理解したうえで選ぶことが大切です。
伝統的な品目
結納返しには古くから定番とされる品目があります。以下の表は、伝統的に選ばれる品目とその意味を整理したものです。
| 品目 | 意味・由来 | 特徴 |
| 末広(扇子) | 子孫繁栄・家庭円満を願う象徴 | 縁起物として全国的に定番 |
| 袴地・羽織 | 男性の正装としての格式を表す | 新郎の社会的成長を願う意味 |
| 時計 | 「共に時を刻む」「時間を大切にする」 | 実用性が高く現代でも人気 |
| 印章 | 社会生活や仕事に役立つ道具 | 一生ものとして記念性が強い |
代表的なものでいうと「長持ちするもの」や「末広がりを象徴するもの」は定番の品といえます。たとえば、子孫繁栄や家庭の発展を願う縁起物で知られている末広(扇子)や、男性用の正装である袴地や羽織、さらに日常生活や社会的な場面で役立つ時計や印章も結納返しの定番であり、仕事や人生の節目に活躍する実用品として人気があります。
これらの品目は単なる贈り物ではなく、結婚という人生の節目を祝う象徴的な意味合いを持つ点が特徴です。
人気の記念品・実用品
現代の結納返しでは、実用性や記念性を兼ね備えた品物が人気を集めています。中でも「長く使えるもの」「毎日身につけられるもの」が選ばれる傾向が強く、贈られた側にとっても思い出と共に日常に根付く存在となります。以下の表は、人気の記念品・実用品の代表例と特徴を整理したものです。
| 品目 | 意味・魅力 | 特徴 |
| 腕時計 | 共に時を刻む象徴、日常的に使える | 記念性と実用性を兼ね備えた定番 |
| オーダーメイドのスーツ | 社会人としての装いを整える | 新生活や仕事に直結する実用品 |
| 万年筆 | 仕事や人生の節目を支える道具 | 長く愛用でき、記念性も高い |
| ビジネスバッグ | 活躍の場を広げるサポートアイテム | 実用性重視、仕事での使用頻度が高い |
| 趣味用品 | 個性やライフスタイルを反映 | カメラ、自転車、アウトドア用品など多彩 |
特に腕時計は「これから共に時を刻む」という象徴的な意味があり、実用品でありながら記念性も高いことから定番になっています。また、ビジネスシーンで役立つオーダースーツや革靴、万年筆なども選ばれることが多く、社会人としての新たな一歩を支える品として喜ばれます。
さらに近年では、趣味やライフスタイルに合わせて選ぶアイテムも増えており、カメラや自転車、アウトドア用品など、相手の個性を反映した結納返しも注目されています。
品物を選ぶときの注意点
品物を選ぶ際には、実用性や記念性だけでなく、贈る相手や両家の価値観に配慮することが大切です。
まず、金額のバランスには注意しましょう。高額すぎる品物は過度なお返しと受け取られかねず、逆に安価すぎると失礼に感じられる可能性があります。結納金の金額や地域の相場を踏まえ、無理のない範囲で選ぶことが基本です。
また、実用品を贈る場合でも、好みやライフスタイルに合わないものは避けるべきです。例えば時計やスーツはサイズやデザインの好みが分かれるため、事前に本人の希望を確認したり、一緒に選びに行くなどの工夫があると安心です。
包装や熨斗の扱いにも注意が必要です。伝統を重んじる家庭では、水引の色や表書きの文字まで細かく気を配ることが求められるため、専門店に相談すると安心です。
品物選びでは「長く使えるかどうか」も判断のポイントであり、結婚後の生活を支えるアイテムは特に喜ばれます。最終的には、形式よりも「感謝の気持ちがきちんと伝わるかどうか」が重要であり、相手に寄り添った選び方を心がけることが成功の鍵となります。
結納返しの品物はいつ渡すの?

結納返しは金額や品物の内容だけでなく、渡すタイミングや方法も重要です。形式に従うか、両家の事情に合わせるかで最適な対応が異なります。ここでは当日と後日の違いや、挨拶の仕方、熨斗や水引の基本ルールについて整理します。
当日に返す場合と後日に贈る場合
結納返しを渡すタイミングには大きく分けて「結納当日に返す場合」と「後日改めて贈る場合」があります。結納当日に返す方法は、最も正式で分かりやすい形式です。新郎側から結納金を受け取った直後に、新婦側から返礼を行うことで、両家がその場で対等な関係を確認できる点が特徴です。儀式としての流れも整いやすく、伝統を重んじる家庭では好まれる方法といえます。
一方、後日に贈る場合は「結納返しの品をじっくり選びたい」「日程的に準備が間に合わない」といった事情に対応できる柔軟な方法です。その際は、結納から1週間から10日以内を目安に届けるのが望ましく、遅れる場合は事前に理由を伝えると丁寧です。後日贈る場合は、宅配で送るよりも新婦本人や家族が直接持参する方が好印象です。どちらのタイミングを選ぶかは両家の意向次第ですが、大切なのは「誠意が伝わる形」で渡すことです。
口上や挨拶文の例
結納返しを渡す際には、感謝と敬意を伝える口上や挨拶文を添えるのが望ましいとされています。
口頭で伝える場合は「本日はご結納をいただき、誠にありがとうございます。ささやかではございますが、感謝のしるしとしてご用意いたしました。どうぞお納めください」といった丁寧な言葉が一般的です。
挨拶状を添える場合は、正式な文書として「謹啓 このたびはご結納を賜り、心より御礼申し上げます。つきましてはささやかではございますが、結納返しをお納めいたしますのでご受納ください」など、格式を意識した表現が好まれます。文章は堅苦しすぎず、気持ちがこもっていることが伝わることが大切です。
最近では略式結納や顔合わせ食事会の場で返礼することもあり、その場合は「本日はお時間をいただきありがとうございます。感謝の気持ちを込めてご用意しましたのでお受け取りください」といった柔らかい表現でも十分です。形式に応じて挨拶のトーンを調整することが円滑な場作りにつながります。
熨斗・水引・表書きの基本ルール
結納返しを渡す際には、熨斗や水引、表書きといった外見の整え方も大切なマナーです。のし袋は紅白の水引が施されたものを用い、結び方は「結び切り」が基本です。これは「一度きりで繰り返さない」という意味があり、婚礼にふさわしいとされています。水引の本数は5本または7本が一般的で、より格式を重んじる場合は7本を選ぶこともあります。
表書きには「御礼」「結納返し」と記すのが一般的で、毛筆や筆ペンで丁寧に書くことが望まれます。記念品を贈る場合も同様に熨斗を添えると正式な印象になります。また、地域によっては表書きの文言が異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
熨斗や水引は細部ではありますが、受け取る側に誠意が伝わる重要なポイントです。品物や現金の内容に加えて、外見の体裁も整えることで、結納返し全体がより丁寧で心のこもったものとして受け取られます。
まとめ
結納返しは、伝統的な儀式としての意味合いだけでなく、両家の関係を円滑にし、新しい生活を円満に始めるための大切な心配りです。
全国的には「半返し」が目安とされていますが、関西では同額返しが慣習とされるなど地域ごとの違いがあるため、両家の意向を確認しながら進めることが重要です。現金だけでなく記念品や実用品を選ぶスタイルも広がっており、形式にとらわれず柔軟に対応する家庭が増えています。 大切なのは、正解にこだわることではなく、相手への感謝を誠実に伝えることです。両家で話し合い、無理のない範囲で心を込めた結納返しを整えることで、結婚準備の第一歩を気持ちよく踏み出すことができるでしょう。